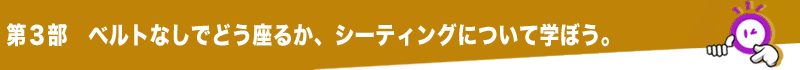
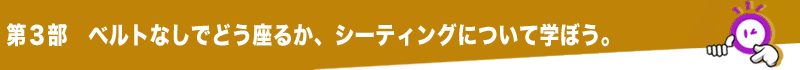 |
| Lesson
15 シーティングの基本知識 シーティングは奥深く短時間で学べるものではありません。私たち介護職はシーティングについて書かれた論文を読むと、なじみのない用語にとまどって理解がなかなかできないこともあります。そこで、鹿児島医療技術専門学校理学療法学科・木下聡美氏に「座位の基本知識」を1項としてまとめてもらいましたので、読んでください。 その上で、表1「車いす座位能力分類」(木之瀬隆 「身体拘束をしない椅子・車いすの使い方」月刊総合ケア Vol.12,No.5,pp23-30,2002より引用抜粋)を頭に入れて、要介護者の座位能力を把握するのです。要介護者にはベッドサイドに端座位になってもらい、1両手を万歳しても座位を保てるのか(座位に問題なし)、2サイドレールを握ったり、ベッド面を自分の手で支えないと座位を保てないのか、(座位に問題あり)、3手を離すなんてとても考えられない状況で座位姿勢がすぐにくずれてくるのか(座位がとれない)、のどれにあてはまるのかを把握しましょう。それだけでもシーティングの視点を持った介護職として第一歩です。
シーティングの知識と技術をインターネット上でどこまで伝えられるか限界はありますが、国立身体障害者リハビリテーション研究所、福祉機器開発部高齢障害者福祉機器研究室室長・廣瀬秀行氏による「シーティング特別講座」をネット上にリンクしました。本稿は、平成14年7月廣瀬先生による講義を私たち研究会が要約したものです。 シーティングは、研修会に参加して実地で学ぶことをおすすめします。東京都立保健科学大学の大津慶子先生・木之瀬隆先生が主催している「シーティングシステム研究会」では継続的に研修会を開催しています。日本社会福祉学会関東部会でも、2004年3月7日(日)にルーテル学院大学で「シーティング研修会」を開催します。学会員以外の方も歓迎です。先着50名です。申し込み方法については後日ネットに掲載します。その他、インターネットでシーティング研修会やシーティングセミナーをキーワードにして検索すると研修会情報を入手することができます。 引用文献に使った木之瀬論文は、車いす身体拘束と普通型車いすの問題点、高齢者の座位能力分類と車いす身体拘束をはずす方法、身体拘束と車いすの課題、について研究と実践をふまえて述べてあるおすすめの文献です。ぜひ図書館等で入手して読むことをおすすめします。また、広く普及しているところでは、厚生労働省「身体拘束ゼロの手引き」2001年 は、廣瀬先生や木之瀬先生たちが身体拘束をなくすための「車いす」や「いす」について書いているわかりやすい文献です。 廣瀬先生のシーティング特別講座
|
||||||||||||||